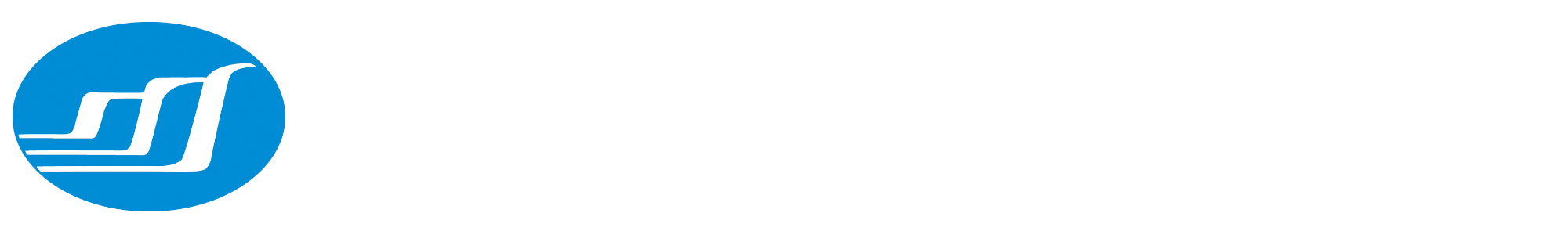「つるみね会」は多くの先輩や運営委員、幹事の努力によって連綿と続く会であり、そのひらがな表記は親しみやすさやアットホームな雰囲気を生み出し、参加者間の交流を促進する効果があると考えられています。また、「つれんかむい」はアイヌ語で鶴嶺の語源とされ、「舞う鶴」と「神」を意味し、鶴嶺高校の命名にも関連しています。
創立時からの鶴嶺高校の様子と「つるみね会」の始まり
創立時からの鶴嶺高校の様子と「つるみね会」の始まり:
創立当初から先生方の指導のもと、生徒たちは伸び伸びと高校生活を送り、一期生も60代になった現在も「鶴嶺」を通じて家族のような繋がりを大切にしている様子が描かれています。
つれんかむい の 由来
アイヌ語で鶴鵠の語源と言われています。
・つれん は「舞う」
・かむい は「神」
鶴嶺高校のある円蔵地域にアイヌの人々が大手を拡げ「つれんかむい」と叫んだであろうと想像します。
「鶴し」は神様、「峰ではない」「領域や集まる」を意味します。
紺碧の空に舞う美しさに、アイヌの人々が大手を拡げ「講讃」と敬意を込めて叫んだであろうと想像します。
※つるみ会の会報を創刊することになった折に、鶴嶺高校を巣立った子どもたちが大自然と調和した新しい時代を作ってくれることを願ってのネーミングです。